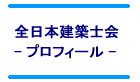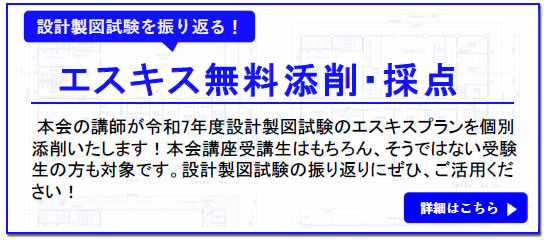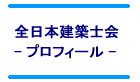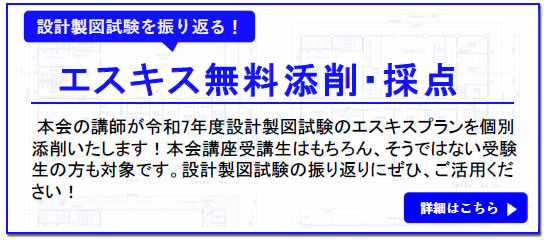合格への鍵 講座 > 本試験の総評 > 設計製図試験の総評(一級)
文字拡大
元に戻す
今年度の本試験の課題は、特に大きな想定外の条件もなく、一見、難易度としては易しいと感じられるものでしたが、この課題条件のような建物を実際に設計するとしたならば、基本設計に何ヶ月もかけて検討することとなると考えられる程に様々な難しい内容を含むもので、試験の場合にどのような採点の基準になるかにもよりますが、相当に難しい建築計画上の内容を含むものであったといえます。
予め試験課題発表時に示された留意事項は以下の4点で、
また、本試験の設計条件としては以下の4点が示されていました。
以上の留意事項、設計条件を踏まえて以下にこの課題の建築計画上、特に留意すべき問題点等についてみて行くこととします。
(1)敷地条件
(2)建物の計画についての条件
(3)要求室
● 本会講座の特長
本講座は、設計(建築計画)及び製図 についての着実な基礎力の養成から着実な合格力の徹底養成を図るものですが、特に近年の試験の傾向から、合格のための重要な鍵となるどのような課題にも共通し、対応できるような基本的な建築計画の考え方、建築計画力の徹底養成を図る内容 となっております。
通学、通信講座ともに全く同一のカリキュラム、内容 で、建築計画力の段階的な徹底養成を図るために作成された全ての演習課題について添削指導 することとしており、また、通学、通信講座ともに全ての演習課題について建築計画上の考え方に重点を置いたWeb動画による詳細なサポート解説を配信する こととしております。
各段階の演習課題の内容は、本会会員の日本建築学会賞受賞者をはじめとする第一級のベテラン講師陣が予め発表された本試験課題の内容を徹底的に分析、検討して作成したもの であるため、演習課題の内容が本試験の課題内容と似たものとなることもしばしばありますが、本講座はあくまでも予想問題やパターン化した事項の記憶のみによる勉強ではなく、着実な建築計画力の養成が合格へ導く最も重要で確実な道である との主旨から構成され、着実な実績を上げております。
● 御社の講座を今回の受験で初めて受講しましたが、それまで受講した講座はどちらかというと、合格のための受験テクニック上のことに重点が置かれていました。御社の講座では受験テクニック上のことに偏ることなく、エスキースの基本的なポイントをしっかり学ぶことができました。また、各課題についての詳しい動画解説もとても役立ち、今回はお陰様で、カド番で合格できました。(1級・設計製図講座・通学)
● 設計製図講座を貴会の通信講座で受講しましたが、添削がとてもすみずみまで丁寧で、また質問にも分かりやすく丁寧に回答していただき、おかげさまで建築計画の力をしっかりと身につけることができました。また、WEBによる各課題についての解説もとても参考になり、合格につながったと思っています。ありがとうございました。(1級・設計製図講座・通信)