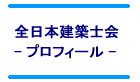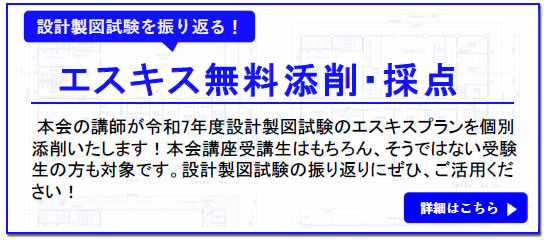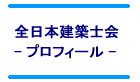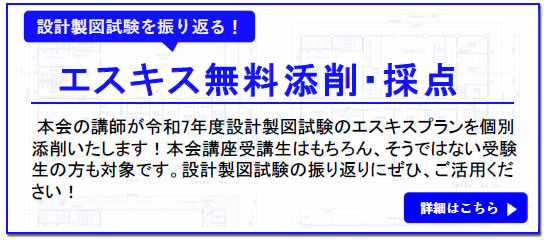令和7年度2級建築士設計製図試験の課題「シェアハウス」の内容は、特段のサプライズといえるようなものは含まれず、むしろ全体的にシェアハウスに特化したシンプルな内容のものであったといえます。
ただし、特にサプライズといえるようなものはなくても、課題の内容をよく見てみますと、建築計画上、事前に単にいくつかの類似の課題を覚えていれば何とかできるというものでなく、以下に記すような点について、真に建築計画の基本的な力が身についているか否かが試される、内容の濃い課題であったといえます。
課題の建築計画上、留意すべき主な問題点としては以下のような点が挙げられます。
(1)建築計画上、自由度の高い課題であることについて
令和7年度の課題は、課題条件として、個室とLDK以外は面積や使用人員の記載がないため、記載のない点については、受験者自身で判断する必要があり、また、敷地に面する2道路の幅員が同一であるため、いずれの道路をメインのアプローチとするかについても、受験者自身で判断しなければならない、建築計画上、受験者の裁量の余地の大きい自由度の高い課題となっています。
(2)敷地の面積と建物の規模について
敷地は、東西15mで南北15m、面積225㎡のやや小さめの設定であるのに対して、建物の延べ床面積は「200㎡以上、250㎡以下」とやや大き目に設定されていることから、建蔽率の制限(60%以下)に注意しつつ、建築面積にも注意しつつ計画を進めることが必要な課題条件となっていました。
(3)敷地の2面に同一の幅員の道路が接していることについて
敷地の西側と南側の2面に道路が接していますが、2つの道路の幅員が異なる場合は、一般的な考え方としては、幅員の広い道路の方から建物の玄関等へのメインのアプローチをとり、幅員の狭い道路の方からは建物の通用口等へのサブのアプローチをとることとなります。
ただし、この課題の場合は、2つの道路の幅員が同一であるため、どちらの道路からメインのアプローチをとり、どちらの道路からサブのアプローチをとるかを敷地の条件を考慮しつつ、受験者が考えなければならず、それだけ受験者の裁量の余地の大きい、自由度の高い課題となっているといえます。
(4)個室が1階と2階にあることについて
この課題は2階建てで、シェアハウスの個室の部分は、1階に広さ13㎡以上の個室を4室設け、2階に広さ18㎡以上の個室を3室設けることが課題条件となっていますが、一般的に個室が2階のみにある場合に比して、この課題のように個室が1階にもある場合は、1階にはシェアハウスの全ての居住者が出入りする玄関や玄関ホール、LDK(共有の台所、食堂、居間)等の共有空間、交流の空間がある一方で、プライベートの静けさを要する個室の空間が共存することとなることにより、一般的に建築計画上の難度は高くなるといえます。
(5)吹抜けを設けることについて
この課題では、LDKのリビングまたはダイニングの部分に吹抜けを設けることとされていますが、吹抜けを設ける場合は、空間上効果的に設けることが重要なポイントとなります。例えば、この課題では、全ての居住者の共有、交流の場としてのLDKを1階の建物の中央部の玄関の近くに設け、2階の交流スペースを1階のLDKの上部に設け、それらを吹抜けを設けて空間的に結び付けることにより、1階と2階の中央部の、交流のための共有空間が効果的に吹抜けにより結び付けられることとなります。
令和7年度の2級建築士設計製図試験の課題は、上記のように特別なサプライズといえるような内容を含むものではなく、むしろ「シェアハウス」に特化したシンプルな内容のものであったといえますが、課題条件そのものについて受験者が自ら判断する必要のある自由度の高い課題となっており、また、敷地の面積に対して建物の延べ床面積が大き目に設定されているなど、単にいくつかの演習の解答例を記憶しておいてそれらを参考にするだけでは対応することが難しく、真に基本的な建築計画が身についているか否かが合否の鍵となる課題となっていたといえます。
● 本会講座の特長
本会の講座は、設計(建築計画)及び製図についての着実な基礎力の養成から着実な合格力の養成を目指すもので、先ず建築法規上の防火、避難等に係わる規定や斜線制限に係わる規定等をしっかり理解することや省エネ設計に係わる基本事項等についての着実な理解力の養成を図るとともに、特に近年の試験の傾向から、合格のための重要な鍵となる建築計画力の徹底養成を図る内容となっております。
通学、通信講座ともに全く同一のカリキュラム、内容で、建築計画力の徹底養成のために、全ての課題について添削指導することとしており、また、通学、通信講座ともに全ての課題について建築計画上の考え方に重点を置いたWeb動画による詳細なサポート解説(各約150分)を配信することとしております。
着実な建築計画力の養成のためには、演習課題の内容のクォリティ(質)が極めて重要となるため、本会講座では、本会会員の日本建築学会賞受賞者をはじめとする第一線の建築家であるベテラン講師陣が、着実な建築計画力の養成を念頭に系統的、段階的に作成する課題から添削指導まで一貫して担当することとしております。
本会講座における各段階の演習課題の内容は、本試験課題の内容を徹底的に検討して作成したものであることにより、個々の演習課題の内容が本試験の課題内容と似たものとなることもあり得ますが、本会の講座はあくまでもパターン化した事項の記憶によるヤマを当てる式の勉強ではなく、着実な建築計画力の養成が合格へ至る最も重要で確実な道であるとの主旨から構成されております。
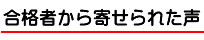
● 御社の講座を今回初めて利用しました。これまで他社の製図通信講座や通学講座も受講しましたが、御社の講座の指導で明らかに優れていた点は、敷地内及び室内のゾーニングや動線で、これまでの敗因はその点だったと気づきました。また、各課題ごとに送信される動画解説も大変参考になり、今回3回目の受験で合格することができました。ありがとうございました。
● 貴会の設計製図の通信講座を利用しましたが、貴会の通信講座では、全10課題の添削がとても丁寧で分かりやすく、また、演習課題は、計画の基本的なことから試験対策にまで十分に対応できる知識を、順を追って段階的に身につけることができる内容で、実際の試験でも、これらの内容で勉強したことで対応できました。また、各課題についてのWEB解説動画もとても参考になり、おかげさまで初受験で合格することができました。
|