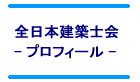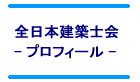|
合格への鍵 講座>本試験の講評>学科試験の講評(一級)
 令和7年一級建築士学科試験は、総じて難度が低かった令和6年の試験に比し、ほぼ例年並みの難度であった学科Ⅲ(法規)以外の学科Ⅰ(計画)、学科Ⅱ(環境・設備)、学科Ⅳ(構造)、学科Ⅴ(施工)の難度は、例年に比し高く、中でも学科Ⅳ(構造)の難度は高い試験となりました。
令和7年一級建築士学科試験は、総じて難度が低かった令和6年の試験に比し、ほぼ例年並みの難度であった学科Ⅲ(法規)以外の学科Ⅰ(計画)、学科Ⅱ(環境・設備)、学科Ⅳ(構造)、学科Ⅴ(施工)の難度は、例年に比し高く、中でも学科Ⅳ(構造)の難度は高い試験となりました。

「計画」は、狭い意味では設計、広い意味では建築のあらゆる分野の計画を意味する訳ですが、学科Ⅰの「計画」は、後者の広い意味で、従って学科Ⅰ(計画)の出題範囲は、他の学科の分野まで非常に出題範囲が広いのが特徴です。
令和7年の出題分野の構成は、ほぼ例年通りの建築史・作品4問、建築計画11問、都市計画2問、設計・監理業務1問、プロジェクトマネジメント1問、積算1問でしたが、特に近年の社会状況に係わる異常気象や自然災害、少子高齢化等に関連する問題として、「省エネ対策」「環境負荷低減」「災害対策」「高齢化社会」等に係わる問題が出題され、また、保存、再生に関連する問題として「建築物の長寿命化」「団地再生」「既存建築物のリノベーション」等に係わる問題も出題されました。
更に、近年、特に重視されてきている木造化に関連する問題として、「木造建築推進」に係わる問題が出題されたのは注目されます。
また、他科目に関連した問題としては、学科Ⅲ(法規)に関連した「全館避難安全検証法」「排煙設備と退避スペース」に係わる問題や「天空率」に係わる問題が出題され、学科Ⅳ(構造)に関連した問題として「耐震改修」や「シロアリ」「木材の腐朽」に係わる問題が出題され、更に学科Ⅴ(施工)に関連した問題として「タイルの分類」に係わる問題が出題されました。

出題構成は昨年と同様の環境工学10問、建築設備10問でしたが、最も今日的なテーマともいえる環境・省エネルギーに関する初出題の問題として、令和7年は「負触媒効果」「エンボディドカーボン」「ホールライフカーボン」「一次エネルギー消費量等級の基準」に係わる問題が出題されました。
更に令和7年の出題の特徴として、初出題の問題でなく、過去に出題された問題であっても、単なる同一の焼き直しの問題ではなく、正解に至るためには単なる暗記でなく、理論に対するより深い理解力を要するように工夫された問題が種々出題された点も注目されます。

法規の出題分野は、例年通りの建築基準法が20問、関係法令が10問でしたが、令和7年の法規の問題で注目される点は、新規法改正に係わる問題で、今回の試験から初めて出題されることになった4月1日施行に関する問題としては「確認申請」「既存不適格建築物」「火熱遮断壁」「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に係わる問題が出題され、また、従来通りの1月1日施行に関する問題としては、「建築手続き」や「防火規定」等についての問題が出題されました。
なお、令和7年の法規の問題では、昨年に引き続き、詳細な規定である告示に関する難度の高い問題が出題されたことは注目されますが、総じて過去問に準じた問題も多く出題され、例年並みの難度であったといえます。

出題構成としては、ほぼ例年通りの構造力学6問、各種構造21問、建築材料3問でしたが、令和7年の構造力学の問題は、概して例年の問題に比して難度の高い問題が多く出題されました。問題の内容そのものは、新規の内容の問題は多くなく、過去問に類する問題が多く出題されましたが、従来の問題に比して、より深い理解力がないと解けないように工夫された「断面の性質」「梁のたわみ」「崩壊荷重」等の程度の高い問題が多く出題されました。
各種構造の問題も、木質構造、RC造、S造、基礎構造等の基本構造種別の他に「プレストレスコンクリート構造」「壁式鉄筋コンクリート構造と壁式プレキャスト鉄筋コンクリート構造」「合成梁」「SRC構造とRC構造の合成」「制振構造・免震構造」は正答肢を含む選択肢が初出題の問題で、難度の高い問題でした。
また、建築材料の問題では、「鋼材の厚さの許容差」を問う問題は、正答肢が初出題の問題でした。

令和7年の施工の問題は、施工計画、施工管理等4問、各種工事20問、請負契約1問の例年通りの出題構成でした。これらの中で、正答肢が初出題となる「セルフレベリング材塗りの養生期間」や「掘削孔の先端深度の検測」等の問題が10問含まれていましたが、他方、過去問に準ずる内容の問題で正答肢が過去問からの問題も多く含まれていました。
正答肢が初出題となる問題であっても、正答肢が過去問からの問題であっても、それらの問題に含まれている過去問に係わる選択肢についての知識等をいかにより深く、正確に理解しているかが問われる問題が多く、難度は例年よりもやや高かったといえます。
なお、近年、重要視されてきている問題として改修工事に係わる問題が本年も2問出題されていたことは今後の傾向を考える上でも注目されます。
令和7年の各科目の出題内容は、単なる過去問についての表面的な知識のみでは解けない、いかにより深く、正確に関連分野を広く理解しているかが問われる問題が、例年に比して多く出題され、総じて例年より難度の高い試験問題であったといえます。
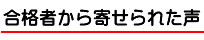
● 2回目の受験で貴会の講座を受けました。今まで受けた講座は過去問のみに偏重していたことが敗因だったと思われました。貴会の講座では、単に過去問のみではなく、より応用力を要する問題にも対応する力を身につけられたことが合格につながったと思っています。ありがとうございました。
● 今回初めて御社の通信講座を受講しました。WEBで配信されたいずれの講義も過去の出題傾向にしっかり対応するとともに、近年の傾向にも対応した解説がとても分かりやすかったと思いました。おかげさまで今回は不得意科目も克服することができ、3回目の受験で合格することができました。感謝しております。
|

|