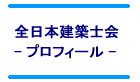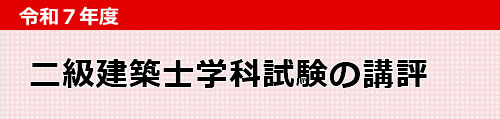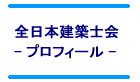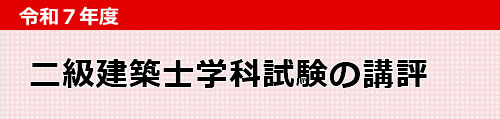|
合格への鍵 講座>本試験の講評>学科試験の講評(二級)
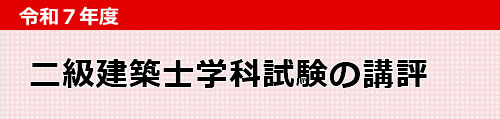
 令和7年度の学科試験問題は総じて、学科Ⅰ(計画)は例年に比しやや難易度は低く、学科Ⅱ(法規)、学科Ⅲ(構造)、学科Ⅳ(施工)は概ね例年並みの難度であったといえます。 令和7年度の学科試験問題は総じて、学科Ⅰ(計画)は例年に比しやや難易度は低く、学科Ⅱ(法規)、学科Ⅲ(構造)、学科Ⅳ(施工)は概ね例年並みの難度であったといえます。
令和7年度の試験問題中で、初出題の問題(正答肢が初出題の問題)は、20%程度で比較的高い割合となっていました。
多くの問題では初出題の選択肢とともに過去に出題された問題の選択肢も含まれており、基礎をしっかり学習した上で、過去問をしっかり学習することにより正答に至ることのできる問題が比較的多かったといえますが、他方、過去問に対する単なる表面的な知識のみではなく、より深い理解や知識を要する問題が相当数含まれていたことから、結局、過去問についての幅広い、深い理解や応用力等をいかに身に付けていたかが合格の鍵になったと考えることができます。
なお、令和7年度の試験問題では、特に4月1日施行の法改正に係わる問題も出題されており、本会の講座でも留意事項としたところですが、当該法改正についての学習を着実にしていることが問われる問題が出題された点は注目されます。

総じて、過去問をしっかり学習していることにより正答に至ることのできる問題が比較的多く出題されており、難度は例年に比してやや低かったといえます。
建築史では、日本建築史と西洋建築の問題が1問ずつ出題され、特に日本建築史の問題では、初出題の難度の高い選択肢も含まれていましたが、桂離宮に同仁斎が含まれているという選択肢は、同仁斎は銀閣の東求堂にあるものであることから誤りで、むしろ過去問としても出題されたことのある基礎的な問題であったともいえます。
環境工学では、過去問としても出題されたことのある基本的な問題が多く出題されましたが、表面的な記憶による知識としてではなく、理論をしっかり理解していることが問われる問題が多く出題されました。
計画各論の問題も、過去問としても出題されたことのある問題が多く出題されましたが、「高齢者や身体障害者等に配慮した建築物の計画」や「都市居住型の誘導居住面積水準」等についての問題など、やや難度の高い新規の問題も出題されました。
建築設備の問題では、「通気管の大気開口部の開放位置」や「泥だめの深さ」についての問題や、電気設備に係わる問題等で比較的難度の高い新規の問題が出題されました。
なお、環境・省エネルギーについての問題は、本年の問題としても出題されましたが、最も今日的な問題として、今後も必ず出題されることが予想されますので特に留意しておく必要があります。

建築法規の問題は、総じて例年並みの難度の問題でしたが、4月1日施行の法改正に係わる問題が4問出題されたことは注目されます。
建築基準法に関する問題では、「防火区画」や「避難施設等」についての問題の正答肢が初出題の比較的難度の高い問題で、また「確認申請」、「構造計算による安全確認」についての問題は、4月1日施行の法改正に
係わる事項が出題されました。
関係法令に関する問題では、近年、重視される傾向にある建築士法に関する問題が本年も例年通り2問出題され、その中の1問は「二級建築士の設計範囲」が広くなったことについての4月1日施行の法改正に係わる問題でした。
更に近年、環境・省エネルギーに係わる問題として特に注目されてきている「建築物省エネルギー基準への適合義務」についての問題も4月1日施行の法改正に係わる事項の問題として出題されました。

一部にやや難度の高い問題も出題されましたが、総じて例年並みの難度の問題が多く出題されました。但し、構造の問題では、あくまでも表面的な知識のみでなく、しっかりした理論への理解が不可欠であることに留意しておく必要があります。
構造力学に関する問題は「静定ラーメンの曲げモーメント図」や「トラスの切断法」等についての標準的な難度の、しっかりした基本的な事項についての理解があれば解ける問題が出題されました。
一般構造に関する問題では、「壁式鉄筋コンクリート造の壁梁」についての問題や「耐震設計の層間変形角の緩和の限度」ついての初出題のやや難度の高い問題が出題され、また、近年、出題頻度の高くなってきている木構造についての問題として「存在壁量に算入できる準耐力壁」、「柱の小径の計算方法」、「筋かいの緊結方法」に係わる問題が4月1日施行の法改正に関する問題として出題されました。
建築材料に関する問題では、「鋼材の引張応力度ー歪度曲線」の問題等、過去問として何度か出題された問題であっても、しっかりした理論への理解がないと解けないような新たな出題形式による問題や各種セメントの初期強度の大小を問う初出題のやや難度の高い問題が出題されました。

総じて、例年並みの難度の問題が多く出題されましたが、一部に初出題の実務上の細かい数値についての知識等を問う問題も出題されました。施工計画、施工管理に関する問題では「ネットワーク工程表」に関する計算問題が5年ぶりに出題されました。
また、材料の保管・管理や廃棄物等の問題は過去問として何度も出題されている問題ですが、廃棄物に係わる問題は近年の環境問題とも関係のある問題として特に留意しておく必要があります。
各部工事に係わる問題としては、近年、特に重視されてきている木造に関する問題が本年も例年通り3問出題されたことが注目され、また、本年は、「高力ボルト締め」や「溶接のエンドタブやスタッド溶接後の検査基準」についての初出題のやや難度の高い問題が出題されたことが注目されました。
積算・見積に係わる問題としては、積算に関する基本的な用語に関する知識を問う問題が出題されましたが、その中で、現場環境改善費の用語の意味が初めて出題されたことには、今日的問題に係わる問題として注目されました。
なお、本年も近年、重視される傾向にある改修についての問題が出題されましたが、今後も出題の可能性の極めて高い問題として留意しておく必要があります。
請負契約に関する問題は毎年必ず1問出題され、本年も近年続けて出題されている監理業務に関する問題が出題されましたが、監理業務における「監理」と建築士法上の「工事監理」との相異点や類似点をしっかり理解しておくことが必要です。
 令和7年度の試験問題は、総じて、ほぼ例年並みの難度の問題が多く出題されましたが、特に4月1日施行の法改正に係わる問題が何問も出題されたことは注目されます。
令和7年度の試験問題は、総じて、ほぼ例年並みの難度の問題が多く出題されましたが、特に4月1日施行の法改正に係わる問題が何問も出題されたことは注目されます。
また、初出題の選択肢を含む問題も種々出題されましたが、その問題の選択肢として過去に出題された選択肢を含む問題も多く、過去問についてのしっかりした理解があれば正答に至ることのできる問題が多く見られました。
その一方で、前述のように、単なる過去問についての表面的な知識では解くことが難しく、より深い理解・知識や応用力がなければ解くことが難しい問題も相当数含まれていたことから、過去問についてのより深い、幅広い理解、知識、応用力をいかに養成し、身に付けていたかが合格への重要なポイントになったものと考えることができます。
|

|