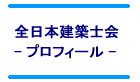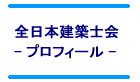��ǯ�ΰ����ۻγزʻ�Ǥϡ�����ν����ϰϤ�Ķ�������������Ƥ������ޤ�����䡢����ν����ϰ��⤫��ν���Ǥ��äƤ⡢��꿼�������Ϥ��פ��������ޤ�������������γ��ǽ��ꤵ���褦�ˤʤä���ޤ�����
��ǯ�λ�Ǥϡ��زʭ��ʷײ�ˡ��زʭ��ʻܹ��ˤˤ����ơ����Τ褦�ʷ����������˸���줿ȿ�̡��زʭ�(�Ķ��������ˡ��زʭ���ˡ���ˡ��زʭ��ʹ�¤�ˤǤ������Ʋ��ν����ϰϤ�������꤬¿����������ǯ�¤ߤ�����٤Ǥ��ä��Ȥ����ޤ���

�ײ�ν���ʬ��Ϸ��۷ײ������¾�����ۻˡ��ԻԷײ褫���߷ס����������Ԥο��դ�ץ������ȥޥͥ���������¿�����Ϥ�ޤ�������ǯ�λ�Ǥϡ��ä˷��۷ײ���������ۻˡ��ԻԷײ��ʬ��ǿ��������Ƥ������ޤ����꤬¿����������٤��⤫�ä��Ȥ����ޤ���
�ä˶�ǯ�Υ��ȥå����Ҳ�������ȿ�Ǥ�������������Ȥ��ơ�����Ū����ʪ����¸�϶�˷��������ϡ������ʷ���������Ȥ��ƺ�������ܤ���ޤ���

�Ķ��������ν���ʬ��ϡ����۴Ķ����ء�������������ʤ�ޤ��������۴Ķ����ؤǤϡ��ä��������Ф�����¤�������פ���ʬ��ǡ���˼Ǯ��١���ʿ�̾��١�����������쥬���˴ؤ�������Ƿ����꤬���ꤵ��ޤ�����
�ޤ������������ϡ��ä˶�ǯ���Ҳ�Ū�ؿ��ι⤯�ʤäƤ��뤳�ȤǤ����ܤ����ʬ��ǡ���ǯ�ϥǥ�����ȶ�Ĵ��PAL������ʪ�ʥ��ͥ륮����ǽɽ�����٤˴ؤ����Ĵ���ʥ��ͥ륮���˷��������ǿ��������Ƥ������ޤ����꤬���ꤵ��ޤ������������ơ����۴Ķ����ء������������˲��ν����ϰ����ɸ��Ū�����꤬¿�����������������٤���ǯ�¤ߤ�������㤫�ä��Ȥ����ޤ���

ˡ���ν���ʬ��ϡ����۴��ˡ�ȷ��۴ط�ˡ�ᤫ��ʤ�ޤ��������۴��ˡ�ϡ�������20�����ǯ�̤�ν�����Ψ�ǡ�����������ŷ�桢���������졢�������˴ؤ��뿷���������ޤ���꤬����ޤ������������ơ����������٤ϳ�����ǯ�¤ߤ��ä��Ȥ����ޤ���
�ޤ������۴ط�ˡ���ʬ��Ǥϡ��ä˷��ۻ�ˡ�˷�������꤬3����ꤵ��ޤ���������ǯ�����ۻ�ˡ���Ż뤵��Ƥ��Ƥ��뷹���Τ�����ǡ�������ä����ܤ���ޤ���

��¤�ν���ʬ��ϡ��ϳء����̹�¤����������ʤ�ޤ�������ʬ��ν�����Ψ����ǯ�̤�ǡ������˥ץ쥹�ȥ쥹�ȥ���ȹ�¤����٥�������˴ؤ��뿷���������ޤ��Τ�ߤ��ޤ����������ͽ�������Ƥ⽾��ν����ϰ��⤫��Τ�Τǡ�����٤���������ǯ�¤ߤǤ��ä��Ȥ����ޤ���
â������¤��ʬ��Ǥ�����˻�뤿��ˡ��������Ф�����¤������Ϥ��Բķ�����꤬¿�����������Ф���μ¤������Ϥ�̵ͭ���������礭���ƶ����뤳�Ȥ�α�դ��Ƥ���ɬ�פ�����ޤ���

�ܹ��Ͻ����Ϣʬ��ä˹������ޤ������Ѹ줬¿�����Ϥ�Τ���ħ�Ǥ�������ǯ�ν������ƤȤ��Ƥϡ��������б�����������̤Ҥ����١�������®�ٷ��������峦�̤ˤ������˲�Ψ�������������Ū���٤����Ƥ������ޤ����꤬¿�����ꤵ�졢���������٤���ǯ�����⤫�ä��Ȥ����ޤ���
�ܹ��Ǥϡ�¿���̤ξܺ٤ʤ��ȤˤĤ��Ƥ����Τ��μ����ˡ��ܹ��������ηи��Τʤ����Ǥ⡢��¤��������ƿȤ��դ��Ƥ������������Τ���ν��פʸ��Ȥ����ޤ���
��ǯ�γزʻ������ϡ������˿��������Ū���٤����꤬���ꤵ��ޤ�������5�������ΤǤϳ����ơ����ν����ϰϤ����ɸ��Ū�����꤬¿��������������٤���ǯ�¤ߤ�������㤫�ä��ȹͤ����ޤ���
â������������٤��㤯��¿���μ����Ԥ�����ʬ�ۤ��⤫�ä����ˤϡ���ʴ������ͽ����������Ĵ��������ǽ��������ʤɡ���ι��ݤϡ�����Ūɾ���ˤ�äƷ�ޤ뤳�Ȥ����Ƥ���ɬ�פ�����ޤ������ʤ�������꤬�פ�����С���ϰפ����ʤ�Ȥ������꤬����л�����ʤ�Ȥ�ɬ����������ʤ����ȡ����꤬�פ�����аפ��������Ȥꤳ�ܤ����Ȥϡ���̿Ū�Ȥ�ʤ����뤳�Ȥ����Ƥ���ɬ�פ�����ޤ���
���ˡ����٤ʿ����������ޤ�����Ǥ��äƤ⡢���������4�ޤ����䤬���ƿ���������Ǥ�����Ͼ��ʤ���¿���ξ�硢��������λޤ��ޤޤ�Ƥ��ơ����������䤬�ʤ��Ȥ⡢�������䤬�������˻�뤳�Ȥ�¿�����Ȥʤɤ��顢���ν����ϰϤ����ɸ��Ū��������˳μ¤������Ǥ��뤫�ϡ������ο����������䤬�뤳�Ȥ�ͥ����Ĥ������˽��פʥݥ���ȤȤ�ͤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
- 2015ǯ7��27�� -
|