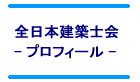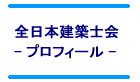|
 設計製図試験受験のためには、まずは学科試験に合格する必要があります。
そして、設計製図試験では、「設計力」と「製図力」の両方が試されます。
当然、受験生の皆様の中には、「平行定規」を使って手書きで図面を描くという作業が未経験の方もいらっしゃると思います。 設計製図試験受験のためには、まずは学科試験に合格する必要があります。
そして、設計製図試験では、「設計力」と「製図力」の両方が試されます。
当然、受験生の皆様の中には、「平行定規」を使って手書きで図面を描くという作業が未経験の方もいらっしゃると思います。
作図未経験者の方が、合格を勝ち取るための「設計力」と「製図力」を身につけるにはどうしたらよいか?自分も作図できるようになるのだろうか?等の不安に駆られるのは当然のことです。
その一方で、作図未経験の初受験者の方が多数、学科試験・設計製図試験を共に一回で合格されていらっしゃいます。以下、設計製図試験合格のために必要な基本的な考え方を示していきたいと思います。
 平成24年に試験実施機関より、二級建築士試験の内容の見直しについての発表があり、設計製図試験においては「設計力」を重視することが、より明確に示されました。 平成24年に試験実施機関より、二級建築士試験の内容の見直しについての発表があり、設計製図試験においては「設計力」を重視することが、より明確に示されました。
受験生の皆様は、試験当日、「課題文」を熟読し、そこに記載されている条件を満たす建物を設計(プランニング)し、ご自身が考えたプランを、解答用紙に「手書きの図面」という手段で表現して、採点官に伝えます。
「課題文」を作成した人と採点官を同一人物とみなすと、採点官が「施主」であり、作図する受験生は、「施主」から建物の設計を依頼(発注)された「設計者」という立場となります。
つまり、「製図力」(作図力)を鍛えに鍛えぬき、きれいで見栄えの良い図面が描けたとしても、その前提にある「設計力」が弱く、要求された条件を満たす建物としてのプランニングが未熟であれば、その方は不合格となる可能性が高くなってしまいます。
 それならば、「設計力」だけを鍛え、「製図力」は程々に、という考えに至ってしまいがちですが、必要最低限の作図力は求められます。 それならば、「設計力」だけを鍛え、「製図力」は程々に、という考えに至ってしまいがちですが、必要最低限の作図力は求められます。
当会の講座では、「製図力」養成のために、開講準備講義において、「線の引き方・テンプレートの使い方・平行定規の使い方」についての動画をご視聴いただけますので、初受験者の方は参考にしてください。
また、「平行定規」や「テンプレート等の製図道具」はご自身でご用意して頂きますが、どのメーカーのものを選ばれても構わないと思います。
 「最後の2枚の作図答案の内、採点官がどちらか1枚のみを合格としなければならないとき、見栄えの良いほうの図面を合格としやすい。」というお話をよく聞きますが、これも、しっかりとした設計力を備えた図面であることが前提であり、「設計力が不足している答案」は、そもそもこのステージには乗ることができません。そこで当会の講座におきましては、合格の為に必要な「設計力」を、10課題に渡り、添削指導・動画解説等をとおして学んでいただきます。 「最後の2枚の作図答案の内、採点官がどちらか1枚のみを合格としなければならないとき、見栄えの良いほうの図面を合格としやすい。」というお話をよく聞きますが、これも、しっかりとした設計力を備えた図面であることが前提であり、「設計力が不足している答案」は、そもそもこのステージには乗ることができません。そこで当会の講座におきましては、合格の為に必要な「設計力」を、10課題に渡り、添削指導・動画解説等をとおして学んでいただきます。
「設計力」養成のためには、自らエスキス・作図を行い、添削指導を受けて自分自身の弱点を知り、その弱点を補うという反復練習が不可欠です。(作図練習は、水泳の練習と同じように、動画視聴・手引書の読み込みだけではダメで、実際に何度も「手」を動かすこと、そして、そのための時間を捻出する努力が必要です。)そして、なるべく早くこの練習に取り掛かる必要があります。「きれいな図面」を書くことだけに注力した学習のみ、作図手順を覚えるだけの学習のみ、では合格できません。
 次のような実例があります。 次のような実例があります。
「図面をとてもきれいに美しく、完璧に書くことができた。ただ、居間が南側に面さずに北側に面していた。」 ⇒ 不合格
「適切な動線計画をふまえたプランニングはよくまとまったが、断面図の梁の寸法を間違えた。又、床伏図の火打ちを1本書き忘れた。」 ⇒ 合格
 概して、設計製図試験では、「設計(プランニング・エスキス)」がしっかりできていれば、作図に多少の減点があっても合格の可能性がありますが、「設計(プランニング・エスキス)」ができていないと致命的な減点となり、不合格となってしまいます。
当会の講座では、製図力向上に注力することは当然としつつ、設計製図試験の合否の重要なカギともいえる「設計力」養成を図ります。 概して、設計製図試験では、「設計(プランニング・エスキス)」がしっかりできていれば、作図に多少の減点があっても合格の可能性がありますが、「設計(プランニング・エスキス)」ができていないと致命的な減点となり、不合格となってしまいます。
当会の講座では、製図力向上に注力することは当然としつつ、設計製図試験の合否の重要なカギともいえる「設計力」養成を図ります。
|